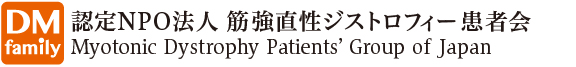学会講演にも登壇!日本神経学会・日本小児神経学会に出展しました
筋強直性ジストロフィー患者会(DM-Family)は、2025年5月21日~24日に行われた第66回日本神経学会学術大会と、6月4日~7日に行われた第67回日本小児神経学会学術集会に出展を行いました。
今年も、会員が協力して展示テーブルの担当を分担し、負担を軽減しながらDM-Familyのパンフレットなどを医療従事者や製薬企業のみなさまにお渡ししました。
また、日本神経学会3日目には、学会内シンポジウムにてDM-Family事務局長が登壇しました。
第66回日本神経学会にて
大阪国際会議場、リーガロイヤルホテル大阪を使った大規模な神経学会に、多くの患者団体が展示参加しました。患者団体同士の交流もあり、お互いに話し合うなど充実した時間を過ごしました。
展示テーブルには多くの方にお立ち寄りいただきました。大会長の大阪大学大学院 望月秀樹先生もお忙しい中でご挨拶にお見えになりました。
望月先生は、筋強直性ジストロフィー治療薬の医師第2相治験で有効性を示した論文の共著者でもあります。会員に向けて励ましのお言葉をいただきました。




神経学会3日目、シンポジウム「PPIがひらく神経難病の明日:病態治療研究への患者市民参画」に事務局長が登壇
医療研究開発において、研究への患者・市民参画(PPI:Patient and Public Involvement)が注目されています。
5月23日早朝、シンポジウム 32「PPIがひらく神経難病の明日:病態治療研究への患者市民参画」にて妹尾みどり事務局長が講演を行いました。
患者会は出展していても、会場に入ることはできません。その会場に、演者の一人として講演をさせていただくことができました。本シンポジウムをご提案いただいた名古屋大学大学院 勝野雅央先生、大阪大学大学院 高橋正紀先生、国立循環器病研究センター 猪原匡史先生に心よりお礼を申し上げます。
講演では、高橋先生からの講演「筋強直性ジストロフィーの治療開発に向けたPPIとその国際連携」をお話しいただいた後、妹尾みどりから「世界中の患者とともに:筋強直性ジストロフィー患者会の取り組み」を発表しました。


籏野あかね理事長の発案でDM-Familyを立ち上げ、研究協力を行い、設立当初から国際筋強直性ジストロフィー会議(IDMC:International Myotonic Dystrophy Consortium Meeting)に参加してきたこと、2021年にIDMCで知り合った海外の患者団体とともに「筋強直性ジストロフィー国際連盟」を共同設立し、日本の患者会として英語サイトを公開、海外患者団体が製薬企業を招聘して現在の治療薬開発状況を聞く会にも参加してきました。

そして学会の直前、5月3日に筋強直性ジストロフィー患者会がアメリカの筋強直性ジストロフィー財団から「Above and Beyond Award」を受賞したことを報告しました。
希少疾患だからこそ、言葉や文化の違いを超え、患者と家族は友人になり、研究参加を続け、困難を乗り越えて行く必要があります。

「自分と家族のことだけ考えていると、病気もわからないし、友人もできないし、治療は近づいてこない。自分のことを話せるようになり、研究に前向きになると、世界は広がり、治療は近づく」と、妹尾事務局長は参加している医療従事者や製薬企業の方に発信し、共感を得ることができました。
第67回日本小児神経学会学術集会
米子コンベンションセンター、米子市文化ホールで行った学会に、今年も非常に多くの患者団体が出展し、交流もさかんに行われました。
どの患者団体も、米子にすぐに行ける会員は多くなく、ほとんどの方が遠路からはるばる参加していました。ほぼ平日の学会に参加するために仕事の都合をつけるなど、工夫する方もたくさんおられます。
DM-Familyでも、有志の会員5名が交代で参加し、会期中の展示を行いました。



先生方から「うちの病院でも、同じ患者さんがいるよ!」とお声がけをいただくと、すかさずDM-Familyで制作した小冊子を手渡ししたり、リハビリについての情報交換をしたりなど、この病気と生活している会員だからこそ、生きた情報をお渡しできます。
患者と家族が学会展示をするのは、難しい話をすることではありません。患者と家族にも、先生方や企業の方にとっても、新しい世界がひらくきっかけです。