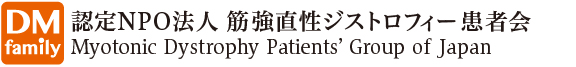第44回東京都理学療法学術大会に出展&都民公開講座に登壇
2025年9月7日(日)、筋強直性ジストロフィー患者会(DM-Family)は、杏林大学井の頭キャンパスで行われた、第44回 東京都理学療法学術大会にブース出展しました。
本大会は、全国の理学療法士や医療介護福祉専門職が参加します。ここに、日常生活上で深く関わりを持つ患者団体のメンバーや医療機器関連の企業の関係者も加わり、総参加者1,500名、対面で1,000名以上もの方が参加されました。

出展した患者団体は23団体。
さまざまな疾患に悩みながらも、前を向き続けているたくさんの患者と家族が集結し、大会を盛り上げました
患者会出展ではそれぞれのブースを訪問して旧交を温めあう、難病に向き合う仲間同士の姿が、会場各所で見られました。
学会への参加は、患者会からの情報提供や提言を通して学術の進展や向上を図る意味を持つばかりではなく、生き方を摸索しながら将来への希望を持ち続けようと日々を送る患者たちが、社会とのネットワークを構築する機会でもあるように感じられました。
筋強直性ジストロフィー患者会は、副理事長の佐藤美奈子が医療用ロボットスーツHAL®でリハビリに励むポスターを作成、これまでのHAL®による成果の資料や会報などとともに展示しました。


大会長の国立精神・神経医療研究センター身体リハビリテーション部 第1理学療法主任 寄本恵輔先生が患者会ブースにご挨拶にお見えになりました。
「午後からは、どうぞよろしく」「はい、がんばります」


国立精神・神経医療研究センター身体リハビリテーション部 有明陽佑先生に、8年に及ぶ佐藤美奈子のHAL®評価の推移をお渡ししました。

19の患者団体が語る【 都民公開講座 期待される理学療法士とは 】
副理事長 佐藤美奈子がHAL®リハビリを通して感じたことは
14時から開催された都民公開講座は「患者会の立場から理学療法士に求めるもの」を軸に、登壇者それぞれが、与えられたテーマに対して意見を述べていくスタイル。
「患者会が講師として呼びたくなる理学療法士とは?」
「小児疾患を抱える親が期待する理学療法士とは?」
など、7つのテーマの中からDM-Familyが指定されたのは
「患者会が補装具、ロボット、車椅子、人工呼吸器、排痰機器などのデバイスが必要な方の視点から期待する理学療法士とは?」というテーマでした。

専門病院で、2017年からロボットスーツHAL®でのリハビリテーションを継続してきた佐藤は、その経験を踏まえ、これまでに感じてきた理学療法士への思いなどを語りました。
関東圏在住の筋強直性ジストロフィーの患者たちは、なぜ関東以外の専門病院にHAL®のリハビリを受けにいくのか?
佐藤は宮城県仙台市の近郊に暮らしており、高速道路を経由すれば30分で到着する場所に、国立病院機構仙台西多賀病院があります。そこで、経過観察のために1年に一度の定期検査を受け、病状の把握や、対処が必要な状態の変化があった場合の措置に備えています。
筋強直性ジストロフィーの自身のデータを、何年にもわたり積み重ね保存している専門病院でのHAL®リハビリを当然のことと思っていた佐藤は、関東圏に居住する筋強直性ジストロフィー患者が、検査やリハビリなどで通院している専門病院でのHAL®リハビリが受けられず、遠隔地へ出かけなければならないことを副理事長として疑問に感じていました。
わたしだったら躊躇してしまうかもしれない
患者が、医療機関やそこに携わる人に求めるものは、知識や技術はもちろんのこと、医療者との信頼関係も重要なポイントとして挙げられます。
「自分をよく知る理学療法士からのリハビリを受けたい」と思うのは素直な本音です。また、数週間に及ぶリハビリを行うための送迎や交通費など、患者と家族にかかる負担も少なくありません。
リハビリテーションの地域格差は、患者にとって大きなマイナスです。住む場所によって、患者が受けられる医療にもリハビリテーションにも差異があり、簡単にその格差は埋めることはできませんが、発言の機会があるのならば、との思いで都民公開講座に参加を申し込みました。

ロボットスーツと患者をつなぐ理学療法士という「人」
佐藤がHAL®でのリハビリを始めてから8年。日常生活を送るうえで、筋力の低下は年を追うごとに増していると実感しているのに、HAL®リハビリの前後で計測する歩行機能の評価数値は変わらずに推移しています。
それは確かな手応えとして喜びにつながる一方で、時として、理学療法士のささいな言葉に息が詰まる思いをしたこともあります。
―「進行性の筋疾患だから、どんなに頑張っても、今より良くなることはない」―
リハビリに過剰な期待を抱き、現実を直視できていない患者に対しては、時に諫めるような言葉をかけたくなるかもしれません。
そんな場合でも、その言葉が今、患者にとってどのような意味を持つかを立ち止まって考えてほしい。
誰に言われなくとも患者自身が、その身に背負っているその言葉の重さを一番知っているということを、常に心にとどめておける理学療法士であってほしいという期待を、佐藤は語りました。

患者団体も患者も家族も、よりよい医療を実現するワンチームの一員として
わたしたち患者と家族にとって、療養生活や身体的な苦痛の緩和、進行性難病とはいえ少しでも維持したい現在の状態を考えると、病院や訪問リハビリなどでかかわる理学療法士はとても大きな信頼を寄せる存在になります。信頼に応える理学療法士であってほしいと、心から願っています。
また、この日登壇した患者団体の代表たちは、それぞれがかかわる理学療法士あるいは作業療法士に、大きな感謝の気持ちも抱いています。
患者とは、医療を、支援を受ける側の人。
理学療法士とは、医療を施し支援にあたる側の人。
そうでありながら、この関係を一方通行の矢印とは考えずに、この社会に求められる理学療法士の姿を、登壇者の意見から明らかにしていこうとする大会長の思いが熱く感じられるシンポジウムとなりました。
そしてわたしたち患者・家族も、社会に向けてさまざまな発信を続けていくべき存在であることを、あらためて考えさせられました。
講演後の患者会ブースに、関東圏でロボットスーツHAL®のリハビリと医療を提供しているという病院からご挨拶をいただきました。理学療法士のみなさまの情報交換として大切な学会ですが、医師も、患者と家族も、ともに学会に参加し、ネットワークを広げていければと考えています。
(筋強直性ジストロフィー患者会副理事長 佐藤美奈子)